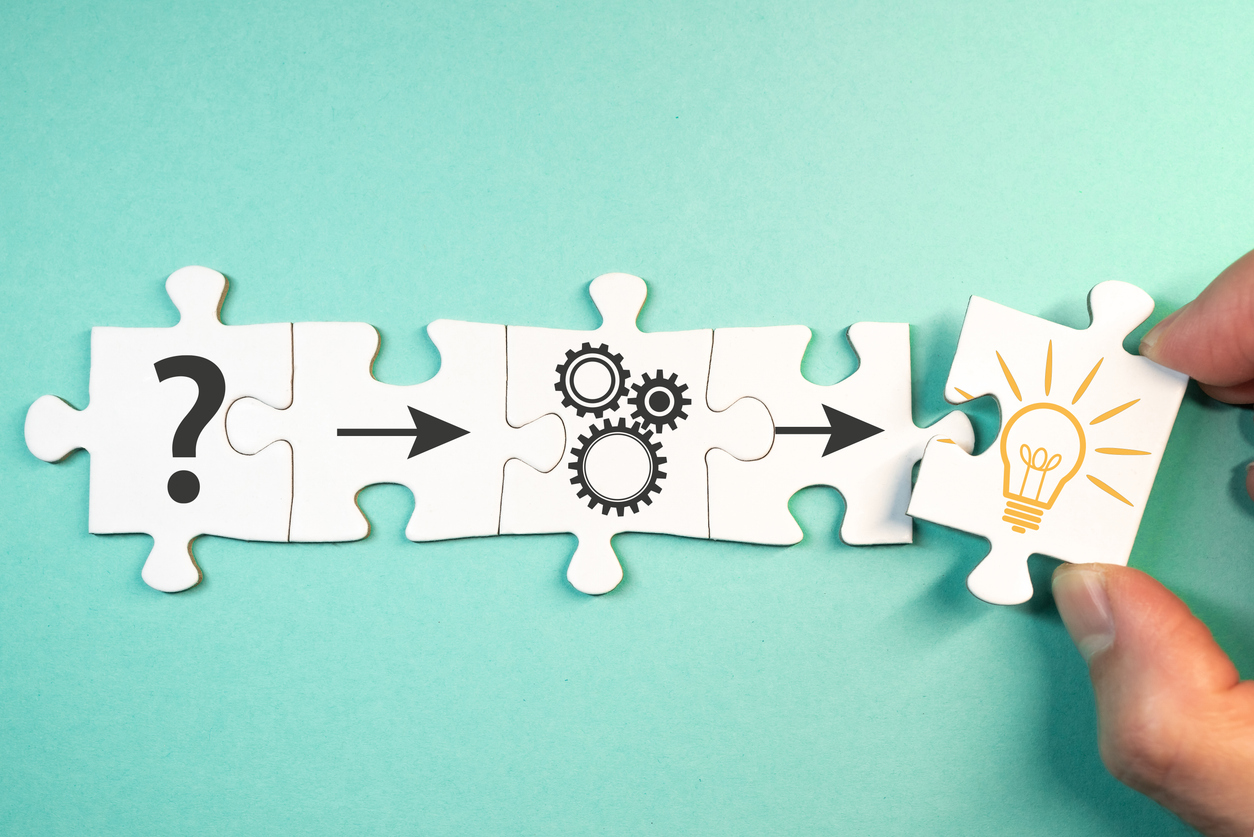
現場データを活用した脱炭素化の進め方
- CO2を算定したい
- 生産設備
- 脱炭素って何からはじめるの?
- コストを削減したい
2025/10/03
中小企業において脱炭素化を進める際、
「現場で日々蓄積されるデータをどのように活用すればよいか分からない!」
という声をよく耳にします。
エネルギー使用量や生産量、稼働状況などのデータは、単に記録するだけでは効果を発揮しません。自社だけのオリジナルビッグデータを活用しないのは、「宝の持ち腐れ」と言うほかありません。
自社のデータを正しく分析し、部門や会社全体で共有・活用することで、省エネやCO2削減につなげることができます。
現場データを活用できる!
ESJの「脱炭素診断」資料請求はこちら
1. 脱炭素化に活用できる代表的なデータ
脱炭素化の取り組みには、以下のような現場データが重要です。
エネルギー関連データの活用
- CO₂排出量の算出
電力使用量(kWh)と燃料消費量(L、Nm³、kgなど)に、排出係数(電力・燃料ごとのCO₂換算値)を掛け合わせることで、事業所や設備ごとのCO₂排出量を算出できます。
- エネルギー原単位
・生産量あたりの電力消費量(kWh/製品1単位)
・生産量あたりの燃料消費量(L(Nm³、kgなど)/製品1単位)
→ 生産効率とエネルギー消費効率の状態や改善状況を追跡できます。
生産・設備データの活用
- 設備別エネルギー効率指標
設備ごとの稼働時間・効率に対する電力使用量や燃料消費量から、
・ kWh/稼働時間
・ t-CO₂/稼働時間
を算出し、省エネ余地のある設備を特定できます。
- 稼働率と排出強度の相関分析
「稼働率が上がると、効率が上がる設備」
逆に「稼働率が上がると、効率が下がる設備」
を把握することで、運用改善ポイントを見つけることができます。
廃棄物データの活用
リサイクル率とCO₂削減効果
- 廃棄物の排出量(kg)とリサイクル率から、廃棄物処理時のCO₂排出削減効果を算出できます。
- 製品1単位あたりの廃棄物排出量
→ LCA(ライフサイクルアセスメント)の基礎データとして利用できます。
これらのデータを組み合わせることで、
- CO₂排出量そのものの算出
- 原単位(生産量あたり・時間あたり)の改善指標
- 設備ごとの効率比較と改善余地の特定
- リサイクルによる排出回避量の算出
などを導き出し、脱炭素化の「定量的な進捗管理」や「対策優先度の明確化」に活用できます。
2. 自社で取得可能なデータとその限界
多くの企業では、電力会社からの請求書や燃料の購入記録からエネルギー使用量を把握していることでしょう。しかし、これらは月単位のデータが中心であり、詳細な分析には限界があります。
また、部門ごとや設備単位での内訳までは把握できず、改善策に直結しにくいのが課題です。
3. エネルギー診断で得られる専門的データの価値
エネルギー診断を受けることで、自社では取得が難しい以下のようなデータの取得も可能です。
・設備ごとの実測データ(エネルギー使用量、CO2排出量、負荷率など)
・工程別のエネルギー効率(稼働状況を見える化し非効率設備の更新や台数の集約等)
・改善余地の明確化(待機電力、消費電力の追従などの運用改善、低負荷率設備の適格容量化)
これらのデータをもとに、省エネ投資や補助金活用を含めた具体的な改善提案が可能になります。
4. データを全社員で共有し問題意識を高める仕組み
データを経営層や管理部門だけではなく製造部門である現場の社員と共有することが、脱炭素化の推進には欠かせません。
また製造部門においても、設備管理者や品質管理部門とのデータや情報を共有することで、改善の手がかりや方向性を確認できます。
例えば、月次で部門ごとのエネルギー使用量を可視化し、改善状況を定期的に発表することで、全員が問題意識をもって取り組む文化が醸成されます。
しかしながら、行き過ぎた改善意識は労働環境に悪影響となってしまう懸念があり、バランスが大切です。
5. ESJが提供する支援と次のアクション
ESJでは、エネルギー診断を通じて現場データを収集・分析し、脱炭素化に直結する改善策を提案しています。また、補助金を活用した設備更新や中小企業版SBT申請支援や脱炭素化計画策定支援など、取引先からの信頼につながる施策の支援も可能です。
まずは、自社にどのようなデータがあり、何が不足しているのかを把握することが第一歩です。詳しく知りたい方は、ぜひESJまでお問い合わせください。
🔍 ESJの「脱炭素診断」資料請求・無料相談
はこちらから
CATEGORYカテゴリー
-
業種でさがす
-
設備でさがす
-
お悩みでさがす
-
導入事例でさがす





 いますぐ電話
いますぐ電話 お問い合わせ
お問い合わせ

